
伯耆町内・指定文化財


| 伯耆町内には、国指定文化財1件、県指定文化財1件、町指定文化財12件があります。全部の現場を探訪し、写真を撮り、マップを作り、紹介記事を書きました。 現地は、地図がはっきりしない所、大変わかりにくい所、山道しかない所、結構探すのに苦労した所もありましたが、近くの人にお尋ねしたりして、何とか全部回る事が出来ました。どうぞご覧くださいませ。 |



| 伯耆町内には、国指定文化財1件、県指定文化財1件、町指定文化財12件があります。全部の現場を探訪し、写真を撮り、マップを作り、紹介記事を書きました。 現地は、地図がはっきりしない所、大変わかりにくい所、山道しかない所、結構探すのに苦労した所もありましたが、近くの人にお尋ねしたりして、何とか全部回る事が出来ました。どうぞご覧くださいませ。 |
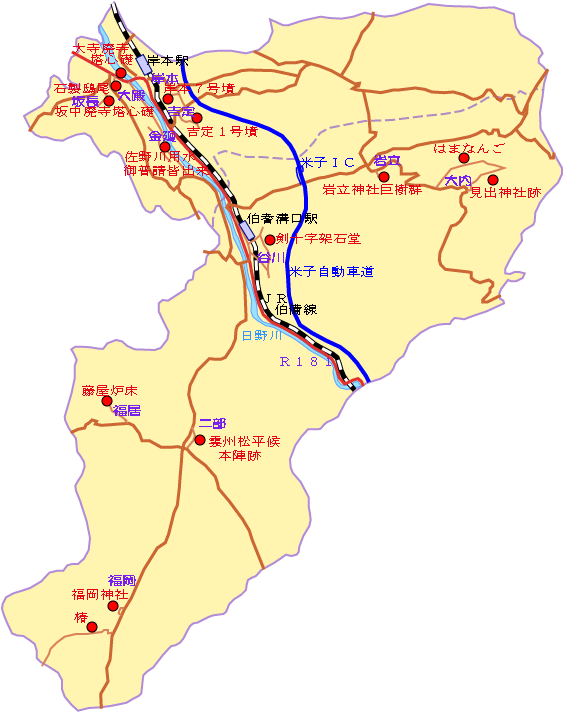
| 説明文の「黒字部分」は現地に立っている案内看板または柱によるものです。 |
| 大寺廃寺・石製鴟尾 (大殿・福樹寺境内) |  | 今から1,200〜1,300年の昔-奈良朝の前期・白鳳時代-仏教が全国に栄え、多くの寺院が建てられ た時代に、この地に大伽藍があった。ここに保存している石製鴟尾はその創建当初の金堂(本堂)の 大棟の両端に飾られたものの一つである。以前福樹寺境内の竹薮に放置されていたものが大正7年 初めて鴟尾として世に知られ、昭和10年には重要美術品に認定され、次いで昭和34年には重要 文化財に指定された。石質は赤色安山岩、全高100cm、基部縦45cm、横77cm。現存の鴟尾は他に 群馬県山王廃寺にその例を見るのみであり、この種の最古のもので、完全な原形をとどめるものとし ても唯一の貴重なものである。この大鴟尾の飾られた寺院がいかに広大であったかをしのぶとともに、 その昔この地方に栄えた高い文化を物語る貴重な史料である。 (昭和34年12月18日 指定) (昭和56年8月1日 建立) |
| 福岡神社神事 (福岡) |
 | 速玉男命(はやたまおのみこと)を祭る福岡神社は、祭神が大蛸に乗って海上を渡来されたと伝え、
俗称「蛸さん」と呼ばれる。10月17日から19日にかけ行われる神事は、「榧取(へぎとり)祭」、
「崩御(ほうぎょ)祭」、「御饌(おそなえ)献上祭」、「大注連(おおしめ)神事」、「蛸舞式」の順で行われ
神秘的な神祭りの古風がよく伝えられており、貴重である。中でも蛸舞式は勇壮な裸祭りで県内では
例を見ない無形民俗文化財である。(昭和61年4月18日 指定)
画像の左下の黄緑の囲みの部分は、建物の右奥にある「蛸の額」をはめ込み合成したものです。 |
| 吉定1号墳 (吉定229番地) |  |
この古墳は細見神社古墳とも言われ、直径約10mの円墳です。封土は一部削り取られていますが、南東に開口した横穴式石室があります。玄室は左片袖式(玄室から羨道を見て)で、奥行5.8m、 奥壁の幅2.2m、高さ1.9mです。扁平な割石を小口積し天上部に近づくに従って持送(もちおくり) がきつくなり、上部には4枚の天井石がおかれています。また壁面には丹彩が認められます。羨道は 一部埋没していますが、1m以内の短いものと考えられます。扁平な割石を小口積した細長い玄室に 短い羨道を持つことは初期の横穴式石室に見られる特徴で、鳥取県における横穴式石室の受け入れ を考える上でも貴重な古墳です。築造は古墳時代中期末ころから後期初めごろと考えられています。 (昭和53年3月30日 指定) (昭和62年3月 建立) |
| 岸本7号墳 (岸本571番地) |  | 岸本7号墳は、岸本古墳群の中心となる古墳です。直径45m、高さ4mの2段に築いた大型の方墳 または円墳で、鳥取県内では最大級の規模を誇ります。古墳の内部は、南に面して両袖式の横穴式 石室があります。玄室は奥行2.76m、奥壁の幅は2.12m、高さ2.39mです。奥壁、側壁、天井は 各1枚の板石で構成され、すきまには小さな割石が詰められています。また、壁面には丹彩が認めら れます。床面には奥の壁寄りに仕切石が立てられています。なお、羨道は埋まって不明です。 副葬品は、見つかっていません。(昭和50年3月25日 指定) (平成2年3月 建立) |
| 大寺廃寺塔の心礎 (大殿・R181号線沿) |  | 大寺廃寺について
1.鴟尾:国指定の重要文化財。石製の鴟尾は全国で極めてまれである。福樹寺境内に保存。 2.塔跡:(イ)塔の心礎径2.4m 柱孔が3段となり舎利孔を有するものは山陰では珍しい。 (ロ)面積140㎡ 瓦積基壇 3.金堂跡:面積162㎡ 4.講堂跡:面積479㎡ 5.回廊跡:礎石群・埋蔵記録保存 6.出土遺物(ハ)葉複弁蓮花文軒丸瓦、重弧文軒平瓦、塑像 残欠、土器他、県立博物館、一部福樹寺保存 今から1,200〜1,300年前奈良時代仏教の興隆により奈良を中心として大和地方には多くの立派な 寺院が建てられ今になお保存されております。ここ大寺の里にも古くから大きな寺があったことは言 い伝えられて塔の礎石、大屋根の鴟尾はすでに発見されていましたが、昭和41年文部省の発掘 調査により奈良朝の前期白鳳時代に、この地に中央にも劣らない堂々たる大伽藍が建立されて いたことがあきらかになりました。(昭和51年3月16日 指定) (昭和45年7月 建立) |
| 坂中廃寺塔の心礎 (坂長822-1番地) |  | 平安時代初期と思われる寺跡にある塔の心礎で、直径1.65mの火成岩で出来ており、中央に径 36cm、高さ10cmの凸部があり、又その中央に径15cm、深さ7cmの円孔がある珍しい型をしてい ます。現在は元の位置から移動したものと考えられ、又、ほぼ中央から二つに割れているのは惜しい が、本町の歴史を解明する上で貴重な資料です。また、この附近からは、柱礎、心礎、蓮華文丸瓦、 唐草文平瓦等の遺物も出土しており、また近くには長者原という地名ものこっていることなどから坂中 廃寺はかつてこの地に栄えた豪族紀氏一門につながる古廃寺であったと推察されます。 (昭和51年3月16日 指定) (昭和63年3月 建立) |
| 佐野川用水 御普請皆出来の碑 (金廻20番地) |  | この記念碑は、文久元年(1861年)佐野川の完成を期して建てられ、正面、左右両側面それぞれ にたくさんの工事関係者の名前が刻まれていますが、文字が不鮮明な個所があります。 この記念碑によりますと、佐野川が竣工したのは文久元年ですから、元和4年(1618年)吉持五郎 佐衛門が長者原開墾に初めて鍬入れをしてから実に約250年を費やしていることがわかります。 この間この偉大な公共事業に多額の私財を投じて尽力された吉持家歴代、池田日向、佐野増蔵を はじめ幾十万人の工事関係者に対し、私たちはその労苦をしのび、恩恵に深く感謝し、永く忘れること なく、子孫に伝えていかなければなりません。(昭和51年3月16日 指定) (昭和62年3月 建立) |
| 岩立神社巨樹群 町指定 天然記念物 (岩立) |  | この神社は、周辺に岩立古墳群、中世の城郭荒堀城があり、また裏山には「岩滝さん」と呼ばれる 古くから信仰された巨石もあり、歴史的環境に恵まれた地にあります。 境内に林立する巨樹は、神社の社叢として古くから親しまれてきました。巨樹群の樹齢は約200年 と推定されています。 もみ:胸高回り・4m 他1本 杉:胸高回り・4.55m 他4本 いちょう:胸高回り・3.7m (平成元年9月30日 指定) |
| 剣十字架石堂 (谷川・道寧寺境内) |  | (昭和52年4月23日 指定)
道寧寺には、キリシタン大名池田輝政以降歴代の位牌も安置されており、境内には、切支丹禁止令により「隠れキリシタン」となった信者たちが仮托(けたく)として日本在来の石堂内部に密かに十字を 彫刻、礼拝した名残が残っており、それがこの剣十字架石堂と伝わっています。(伯耆町HPより) |
| はまなんご 町指定 天然記念物 (大内) |  | 一見、岩塊を積み上げ、石組みをした小山のように見えるが全部同じ岩石で出来ており、割れ目や節理の傾向に規則性があり、自然に出来た岩石で古期(約40万年前)の大山火山の安山岩溶岩が 裾野面から突出しているものである。「はまなんご」の意味はよくわからないが、岩陰には祠が祭られ 浜灘宮、浜灘吾とも呼ばれている。 (平成元年9月30日 指定) |
| 見出神社 (大内) (大江川・一の沢橋の 右岸上流) |  | 見出神社の祭神は、思兼命、大山祇命、大平神、君穂神の四柱といわれています。後醍醐天皇が隠岐を脱出し、船上山から都に向けて出発の途中忍びで、この地の中原太平(元弘の戦に数々の 戦功があって、天皇から勅を賜った勇士)のところに立ち寄られた。太平は大変恐れ入って、心から おもてなしをいたしました。天皇は大変気に入られたご様子で「よい所を見出した」といって、この地を 「見出」と名づけられたといいます。天皇の御座所は、この神社の境内にあったと伝えられています。 (平成元年9月30日 指定) |
| 藤屋炉床 (福居字鑪原471) |  | 昭和52年に道路拡張工事で発見されたもので大舟、小舟が半分以上破壊されていたが残存部分 を昭和53年町文化財に指定。川からずいぶん高い台地上にあり西にわずかな壁が見られる。南北 は崖で南側には製錬滓が多い。北はゆるやかな水田が続き15㎡程の平坦面がある。たたら本床部 分は、大きな掘り込みの中に小舟を東西に置き、中央に大舟を置いてその上に本床をのせる典型的 な釣床形式である。小舟や大舟の裏込めに製錬滓の大きなかたまりを利用しており、すでに近くで たたらが操業されていたことがわかる。本床の北側の平地に長さ2m、幅0.7m、厚さ0.5mの飡 (けら)が放置してある。 (昭和53年9月2日 指定) |
| 雲州松平候本陣跡 (二部) |  | 当足羽家は寛永16年(1639年)ごろから代々出雲松平候の本陣として、その宿泊にあてられた。 当時の本陣の家構えはほとんど改造されているが、わずかに残る主家に格調の高い構成をとどめて いる。 (昭和52年7月20日 指定) |
| 椿 (福岡) |  | この椿は、樹齢はわからないが、古くからこの地にあったと伝えられている。
(平成元年9月30日 指定)
近くにお住まいの所有者の方に聞くと、樹齢は400年位ではないかということです。(筆者 記) |