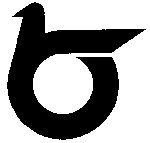ひみつ:その1 |
鳥取県は古くは東の「因幡」と西の「伯耆」の二国に分かれていました。 「因幡」は、法美郡稲羽郷(現:国府町)に国府が置かれたことから、 「伯耆」は、古くは「ハハキ」と言ったようです。 「因幡」と「伯耆」をまとめて鳥取と呼ぶようになったのは江戸時代に入ってからです。 鳥取郷の由来は、鳥を取って朝廷に献上する品部 |
ひみつ:その2 |
飛ぶ鳥の姿を平仮名の「と」に造形したマークで、 |
ひみつ:その3 |
水鳥の一種で、県内の沼や池に住む保護鳥です。 美しく、平和な姿をした鳥で、年中県内に生息していることから、 県鳥獣審議会が昭和39年に選定しました。 |
ひみつ:その4 |
県の産業・生活に関係が深く、県下のどこでも見られ、 県民に広く愛され親しまれている花として、 NHK・全日本観光連盟・交通公社・植物友の会が昭和29年に選定しました。 |
ひみつ:その5 |
イチイ科に属する針葉樹で高山に生育しているが、挿し木による繁殖も容易な木です。 四季を通じて美しく清潔感にあふれ、風雪に耐えて強く伸びゆく姿は 本県の自然美を代表し発展にも繋がるとして、 県と県緑化推進委員会が昭和41年に選定しました。 |
ひみつ:その6 |
面積:3,497.65平方キロメートル(全国41位) 人口:約62万人(全国47位) 年平均気温:14.9℃(全国28位) |
ひみつ:その7 |
起伏日本一の海岸砂丘:鳥取砂丘(起伏量最高92m) 面積日本一の池:湖山池(面積6.8平方キロメートル) 鰯水揚げ日本一:年間約560千トン。全体水揚げ量は全国3位。 |