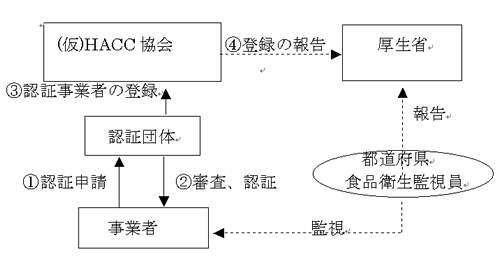
丂俫俙俠俠俹擣徹傪岤惗徣偼儅儖憤乮憤崌塹惗娗棟惢憿夁掱乯偲偟偰俆昳栚偺怘昳擣徹傪梌偊偰偄傞丅枖柉娫偵懡偔偺俫俙俠俠俹擣徹婡娭偑偁傞丅
丂偟偐偟丄愥報帠審偱傕棟夝偟偰偄偨偩偗傞傛偆偵崙偵傕怘昳偛偲偵偡傋偰傪挷嵏偡傞擻椡偼側偄偺偱偼側偄偐丅枖丄怘昳偵偼椻搥怘昳偺傛偆偵斖埻偺峀偄傕偺偐傜媿擕偺傛偆偵岺掱偑扨弮側傕偺傑偱偁傞丅媿擕丒擕惢昳偱偡傜崙偺挷嵏偑姰慡偱偼側偄偺偵丄怘昳嬈奅偡傋偰傪俫俙俠俠俹擣徹偡傞偺偼柍棟偱偼側偄偐丅枖抧曽偱偼恖岥50枩恖偦偙偦偙偺導傕偁傞偑丄偦偙偵拞墰偐傜戝偒側怘昳婇嬈偑恑弌偟偰棃偨応崌丄抧曽偺曐寬強偺栶恖偑娗棟偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅
丂堦曽丄擔杮偺怘昳塹惗朄偼偁傑傝偵帠嬈幰婑傝偱柍愑擟偱偁傝丄徚旓幰棙塿傪枮偨偟偰偄傞偲巚偊側偄丅埨堈偵擣壜傪梌偊偰偄傞傛偆偵巚偊傞丅
丂擔杮崙寷朄偵偼崙柉偺惗柦偲嵿嶻傪庣傞帠偑鎼偭偰偁傞偑丄傑偝偵怘昳偵傛傞怘拞撆巰偼朄偑崙柉傪庣傞尨揰偵掞怗偡傞栤戣偱偁傞丅怘拞撆巰偱孻帠帠審偵偮側偑偭偨偺偼丄塩嬈嫋壜掆巭帪偵惢憿偟偨応崌傗僼僌拞撆摍偵尷傜傟偰偄傞偺偼偳偆偟偨偙偲偐丅
丂巹偼崅埑僈僗庢掲朄傪曌嫮偟偨傕偺偩偑丄捠嶻徣偱偡傜婋尟暔傪庢傝埖偆偵偼偦傟側傝偺柶嫋偑嬈幰偲屄恖偵梌偊傜傟偰偄傞丅慠傞偵怘拞撆帠屘偵娭學偡傞怘昳塹惗朄偵偼丄怘昳塹惗庢埖幰偲偐偱偍拑傪戺偟偰偄傞丅傕偭偲嬈庬偛偲丒婇嬈婯柾偵墳偠偨庢埖柶嫋偑昁梫偱偼側偄偐丅
丂徍榓22擭偵惉棫偟偨怘昳塹惗朄偼婇嬈婯柾偑戝偒偔側偭偨尰戙偵偍偄偰丄枖怘昳偺僌儘乕僶儖壔偵懳墳偟偰偄側偄偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅岤惗徣峴惌偵偍偗傞堛椕塹惗偼傗偨傜偵尩偟偔丄枖堛巘柶嫋偺嬈柋斖埻偑峀偄偺偼擔杮偩偗偲巚偆偑丄摨偠惗柦偵娭偡傞怘昳塹惗朄偼偍偞側傝偱偁傞丅巹偼崙偵傛傞惂搙偺嫮壔傪尵偆偮傕傝偼側偄丅傕偭偲怘昳嬈奅偺奺僕儍儞儖枅偵柉娫偺堄尒傪庢傝擖傟丄枖偦偺婇嬈婯柾枅偵柉娫偱嶌傞柶嫋惂搙傪嶌傝偦傟傪崙偑娫愙揑偵擣傔傞惂搙偑昁梫偱偼側偄偐丄俫俙俠俠俹偼尦乆俶俧俷偱寛傑傞偺偑悽奅揑偱偁傝丄側偤岤惗徣撪偵儅儖憤揑側峫偊偑弌偰偒偨偺偐偼峫偊偵嬯偟傓丅
丂怘昳塹惗朄偺拞偱俫俙俠俠俹偺強偩偗側偤偐峫偊曽偑堎側傝丄堦偮偺朄偺拞偵擇偮偺僗僞儞僟乕僪偑偁傞傛偆偵巚偊傞丅
丂巹偲桳巙偺幰偑峫偊偨怴偟偄俫俙俠俠俹擣徹惂搙偵偮偄偰偺堦埬傪壓婰偵嶲峫偲偟偰壛偊偰偍偔丅
HACCP柉娫擣徹惂搙儚乕僉儞僌G
嘆柉娫擣徹偺昁梫惈偵娭偡傞専摙乮嶰栘巵傾僪僶僀僗偺審乯
丂柉娫擣徹惂搙偺昁梫惈偵偮偄偰偼儚乕僋僔儑僢僾帪偵偍偗傞宱夁愢柧梡偲偟偰嶌惉偡傞丅丂丂撪梕偼奺儊儞僶乕偐傜採弌偝傟偨儚乕僋僔乕僩偺撪梕傪惍棟偟偰嶌惉偡傞丅(慜夞偲摨條)
嘇擣徹偺婎弨
丂丒僜僼僩乮塣梡乯丄僴乕僪乮巤愝乯偺椉柺傪怰嵏偡傞丅
丂丒偙偺婎弨偼儅儖憤偲堘偭偰丄擣徹儗儀儖傪儔儞僋暘偗偟偰拞彫婇嬈偵傕懳墳偱偒傞傛偆攝椂偡傞丅椺偊偽A僋儔僗擣徹丄B僋儔僗擣徹偲擣徹偺儗儀儖傪俀乣俁抜奒偵愝掕偟丄娗棟儗儀儖偵墳偠偨擣徹傪偍偙側偆丅偨偩偟丄HACCP偱昁梫偲偡傞昁梫嵟掅忦審偼奺儔儞僋偲傕梫審傪枮偨偡偙偲偑忦審偲側傞丅
丂丒摉柺丄ISO偺擣徹偲HACCP偺擣徹偼惈奿偑堎側傞偺偱丄崿棎傪杊偖偨傔屄暿偵峴偆偙偲偲偡傞丅
嘊擣徹抍懱偲側傞斖埻乮側傞偙偲偑弌偒傞慻怐乯
屻弎偺擣掕婎弨傪枮偨偡偙偲傪忦審偵慡偰偺朄恖偑懳徾偲側傞丅
丂椺乯専嵏嫤夛丄専嵏惪晧婡娭丄ISO怰嵏搊榐婡娭側偳
嘋擣徹抍懱偺擣掕曽朄偲懱惂乮慻怐乯峫偊曽偺婎杮偼師偺偲偍傝偱偁傞丅
丂丒擣掕偼擣掕傪怽惪偟偨抍懱丄朄恖偵偮偄偰(壖)HACCP嫤夛偑怰嵏偟丄擣掕婎弨傪枮偨偟偨抍懱丄朄恖偵偮偄偰岤惗徣偵擣掕傪怽惪偡傞丅
丂丂岤惗徣偱偼乮壖乯HACCP嫤夛偺怰嵏寢壥偵栤戣偑側偄偙偲傪妋擣偺偆偊丄彸擣傪捠抦偟丄搊榐偡傞丅
丂丒曐寬強偺怘昳塹惗娔帇堳偼擣徹偝傟偨婇嬈偵偍偗傞HACCP曽幃偺塣梡忬嫷傪峴惌偺棫応偱娔帇丄巜摫偡傞丅娔帇偺寢壥栤戣偑偁傟偽丄擣徹抍懱偍傛傃婇嬈偵懳偟丄夵慞偺巜帵傪偍偙側偆丅傑偨丄夵慞偑擣傔傜傟側偄応崌偼岤惗徣傪捠偠丄HACCP擣掕怰嵏夛偵擣徹偺庢傝徚偟傪媮傔傞偙偲偑偱偒傞丅
丂丂亙怽惪幰偺擣徹亜
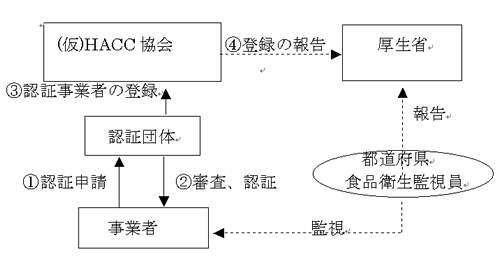
亙擣徹抍懱偺擣掕亜
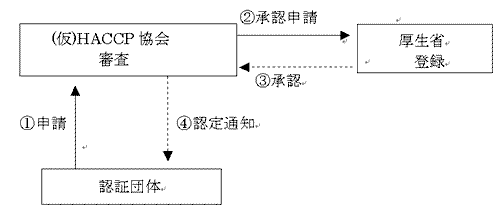
嘍HACCP怰嵏堳偺擣掕
丂丂乮壖乯HACCP嫤夛偑庡嵜偡傞擣掕怰嵏傪庴偗丄怰嵏婎弨傪枮偨偟偨幰偵偮偄偰
丂丂丂怰嵏堳偲偟偰擣掕丄搊榐偝傟傞丅擣掕偝傟偨怰嵏堳偼岤惗徣偵搊榐偑曬崘偝傟傞丅
丂丂丂擣掕偺棳傟偼帠嬈幰偺擣徹偲摨偠丅
嘐(壖)HACCP嫤夛偺栶妱
丂丒擣徹抍懱偑擣掕婎弨傪枮懌偟偰偄傞偐偺怰嵏丄擣掕
丂丒擣掕婎弨偺夵掶偵娭偡傞彸擣
丂丒擣掕抍懱偺擣掕偺庢傝徚偟偵娭偡傞怰嵏
丂丒HACCP怰嵏堳偺怰嵏丄擣掕
仏埲忋偺嘆乣嘐偵偮偄偰WG撪偺堄尒偺堦抳傪傒偨