
*風鈴*
小さな陶器の風鈴。
焼きも、上薬も、品質が悪くいびつで安っぽい。
それがまた今の物にはない風情で愛おしい。
拾ったときには紐も紙も風化してしまっていたので
新しいものをつけてさっそくベランダに。
リン・・・リン・・・と、可愛い音を響かせます。

*水筒*
以前からほしかった、駅で売っていた昔の陶器のお茶の入れ物。
これがまさか拾えるとは。拾い物で運を使い果たしていそうで怖い。
本当は同じ陶器製の蓋をかねたコップと、針金の取っ手がついていたはずです。
*古いもの*
・・・拾い物・・・
なんでもかんでも拾っているようでいて、
実は私なりの拾い方のポイントがあります。
それは、なるべく古いものを拾う、ということ。
骨董屋さんで買ったといってもおかしくないような掘り出し物(拾い出し物?)に
出会ったときはとびあがるほどうれしいです。

*風鈴*
小さな陶器の風鈴。
焼きも、上薬も、品質が悪くいびつで安っぽい。
それがまた今の物にはない風情で愛おしい。
拾ったときには紐も紙も風化してしまっていたので
新しいものをつけてさっそくベランダに。
リン・・・リン・・・と、可愛い音を響かせます。

*水筒*
以前からほしかった、駅で売っていた昔の陶器のお茶の入れ物。
これがまさか拾えるとは。拾い物で運を使い果たしていそうで怖い。
本当は同じ陶器製の蓋をかねたコップと、針金の取っ手がついていたはずです。

*かまどの蓋*
近所の道端に、ずっと前から捨ててあった鉄の塊。
あまりにもひどくサビが浮いていて、ただのサビのかたまりにしか見えなかったので
その存在に気づいてからも拾おうとは思わずにいました。
しかし、ある日何気なく持ち上げてみると思いのほかずっしりした手ごたえ。
サビの中には何か鋳物のものが隠れているに違いない!と感じ、持ち帰ってひたすらサビ落とし。
まる二日がかりでサビを削り落としていくと、昔なつかしのかまどの蓋が現れました。
しかも私の大好きな波千鳥のオマケつき!
今では一番のお気に入りです。

*小さな瓶たち*
インクビン、薬ビン、化粧水のビン・・・
昔のビンは、ゆがんでいたり気泡が入っていたりと
ひとつひとつに温かみがあります。
しかし、中にびっしり入った土を取って
ここまできれいにするのは一苦労です。

*クリームの瓶*
昔の化粧品のビンです。
クラシックで重厚なデザインで
今のものより高級感がありますね。

*碍子(がいし)*
がいし。電柱や電気配線などに使ってある絶縁体です。
どれも古いもので、白磁のとろっとした肌が美しいですね。
これも落ちているものは割れていることが多く、なかなか数が集まりません。
子どものころに近所の空き地にいろんな形の碍子が捨ててありました。あれ、拾っとくんだったなあ。
ところで昔ながらの木製の電信柱って今でもあるんでしょうか?
気になって外出時に探してみましたが、うちの近所ではみつかりませんでした。

*おはじき*
昔のおはじきには、今のものには無い味わいがあります。
いびつな形がカワイイですよね。
ビー玉もとても頻繁に拾うんですが、こちらは古いものかどうかの見極めがむずかしいです。
どれもまん丸ですからね。

*釘?*
たぶん釘ですが、どうやって使ったらこんな形に曲がるんでしょう?
ちなみにまっすぐに伸ばしたとしたら30cm近くあります。
錆びてぼろぼろですがなんとも不思議な曲がり方が気になって拾って帰りました。
銀杏細工の小鳥も心なしかうれしそうに見えます。

*鉄の鳥*
これ、なんだかわかりますか?錆び錆びになって風情たっぷりの鳥さん。
これを道で拾ったときはさっぱり何なのかわからなかったのですが、
つくつくの好きな鳥モチーフの拾い物に大興奮でした。
その後、近所のお寺に行ったおりに軒下に吊られている灯篭を見てびっくり!あの鳥さんがいる?!
よく縁側の外の軒下に鋳物製の家みたいな形の灯篭が吊り下げてありますよね。あれです。
私が見つけたのは、錆びて分解した側面の一面が捨てられたものだったのです。
現役で使われているものがあるということは、これも時代はそう古くないのでしょうが、お気に入りの一品です。

*水滴*
書道で使う水を入れる道具です。
土に埋もれて長年たったのでしょう。桜と蝶の図がすっかり薄くなってしまっています。
これを見つけたのは島根県のとあるお寺の参道脇の藪の中。
土の中に大部分が埋まっていましたが、
チラッと見えた白いものを見逃さなかった自分をほめてあげたいっ!という瞬間でした。

*錘(おもり)*
どんぐりの背比べみたいでしょ。これは焼き物の錘(おもり)です。大きさはひとつ4〜5センチ。
漁をする網につけて使われたもので、近所の空き地にぼろぼろに腐った網ごと捨てられていました。
茶色の釉薬はお隣の島根県で昔から焼かれている石見焼きの特徴です。
山陰ではこの釉薬を使った瓦(赤瓦)が伝統的につかわれてきました。
古い家の赤瓦はこの錘のように一つ一つ微妙に焼きムラがあって、なんともいえない風情があります。
今は新改築すると黒い瓦に変えるお宅が多いので、昔ながらの山陰の家並みが見られないのは残念です。
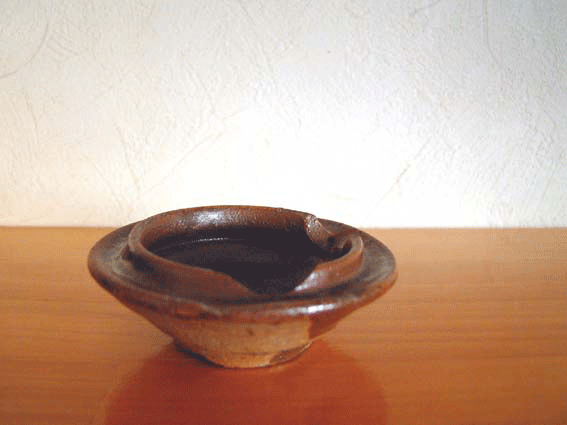
*灯明皿*
こちらも石見焼です。石見焼きは大きな水がめ(はんど)で有名なのですが、いろんな生活雑器も焼いていたようですね。
これはあんどんの中に入れて使われた灯明皿のようです。
手前のくぼみは欠けてしまった部分ですが奥のくぼみは最初からのもので、
このくぼみに芯を置いて、そこに火をつけて使われたようです。
化け猫があんどんの油をなめる話の、油の入った皿がこれです。
なぜかこれも、近所の路地に落ちていました。