| |
|
| むし歯(う蝕)の原因 | |
1:むし歯のプロセス 2:むし歯の三大要因 A:食事と酸の産生 B:おやつの食べ方 C:キシリトールとは? D:唾液について E:フッ素とは? |
|
| 1:むし歯発症のプロセス | |
| 今まではこのプロセスの結果できてしまったう窩(むし歯)の修復に重点を置く診療が主流でした。 しかし、これからはう窩のプロセスを停止させることで、健康な歯を守る診療こそ求められています。 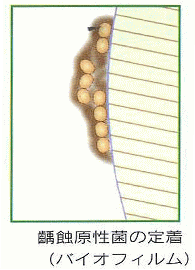 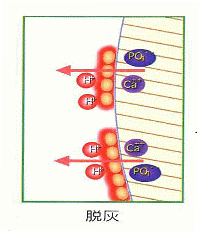 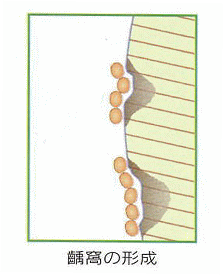 「実践カリオロジー」より引用 |
|
| 2:むし歯の三大要因 | |
むし歯ができるというのは、歯の表面のエナメル質が脱灰して歯質が崩壊することです。 この脱灰には次の3つの要因が関与します。 (1)細菌 ミュータンス菌、ラクトバチルス菌 (2)基質 食物(砂糖ほか) (3)宿主 歯質、歯列、唾液、フッ素の使用 これらのすべての要因が存在したときに、むし歯(う蝕)が発症します。 |
|
| (1)細菌 人の口の中には多くの細菌(300〜400種)が棲息していると言われています。 それらの多くは何らかの理由によって人と共生しているとも考えられ、すべてが有害というものではありません。 しかし、場合によっては色々な疾患の原因となり、口腔内では以下の細菌によってむし歯(う蝕)が発生します。 ・ミュータンス菌(SM : Streptococcus mutans) 性状 大きさは0.5〜10μmの球状の菌で横につながって分裂します。全身疾患の原因にもなります。 きわめて強い歯牙への付着能を持ち、これがう蝕病原性を発揮させます。 むし歯(う蝕)発生にもっとも強く関与する細菌です。 う蝕病原性 最初にミュータンス菌は砂糖をグルカンという物質に変えます。 グルカンは非水溶性で粘着性が高く、きわめて固体に付着しやすいという性質の多糖体で、 水に溶けない糊のようなものです。 ネバネバのグルカンは、エナメル質の表面にミュータンス菌や他の細菌をたくさん付着・増殖させることになります。 ミュータンス菌のう蝕病原性の特徴は 1.強い歯面への付着能 菌体表層に作るタンパク抗原(PA)で付着。グルコシルトランスフェラーゼ(GTF)で スクロースから合成する水不溶性グルカンによる歯面への頑固な付着。 2.強い酸産生能 スクロース(ショ糖)、グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)などから乳酸を 産生しpHを低下させて脱灰を起こす。 3.酸のデンタルプラークでの停滞 水不溶性グルカンはプラークからの酸の拡散を防ぎ、局所に停滞させる。 4.持続的な酸産生能 局所のpHの低い環境でも乳酸を作る。環境にスクロースなどが豊富な場合は菌体内に 多糖体として貯蔵し、環境に糖がない場合は多糖体から酸を産生し続ける。 母から子への感染 ミュータンス菌のほとんどは19〜31ヶ月(2歳前後)に定着します。 この期間にミュータンス菌の感染に気をつけて、他の菌の定着を図ればよいです。 母親の口腔内のミュータンス菌の菌数が多いほど感染率は高まり、少ないほど子供の菌保有率も減少します。 すなわち、子供のむし歯予防にはまず母親のむし歯治療または予防が必要なことが分かります。 母親の口腔を清潔にすることで、子供への感染を減少させることができます。 母親に対するむし歯治療や口腔衛生指導は、妊娠中あるいは出産直後から行うことが望ましいと考えます。 ・ラクトバチルス菌(LB : Lactobacillus) 性状 幅0.4〜0.6μm、長さ2〜3μmのものが多い。 う蝕病原性 感染の第1歩である歯面への定着性が低いため、平滑面う蝕原因菌の主役からは降ろされました。 しかし、いったん出来たう窩や軟化象牙質などからは高頻度で検出されているため、 う蝕の拡大に関与していると考えられています。 |
|
| (2)基質 プラーク中の細菌は摂取された砂糖または炭水化物を代謝して、酸や毒素を産生します。 酸はプラーク直下のエナメル質を脱灰します。 毒素は口臭などの原因になります。 このように摂取された基質によってう蝕の原因となる酸が産生されますが、基質の種類や摂取方法によって う蝕の発生に差が出てきます。 ・食事と酸の産生 臨界pH・・・歯牙が脱灰を始めるpH 乳歯、幼若永久歯、象牙質 ・・・・pH5.7〜6.2 永久歯 ・・・・pH5.5〜5.7 砂糖液による洗口時の歯垢pHの変化 下のグラフは、ステファンカーブとして知られている、砂糖水でうがいをしたときのプラーク中の pHを表したグラフです。 青い線は0.1%の砂糖水、赤い線は5.0%の砂糖水で洗口した時のpHを表しています。 うがい後約2分でpHかなり低下しますが、糖濃度の高い方が回復までにより長い時間を要します。 一般に市販されている清涼飲料水は約10%の糖分が含まれていると言われていますので、 このグラフ以上にpHの低下する時間は延長してよりう蝕の発生の危険性が高まります。 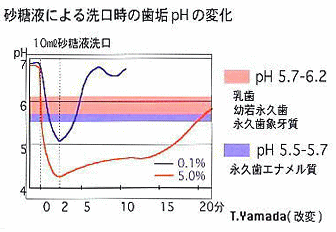 食事の回数とpHの変化 食事回数の増加(間食)は継続的なpHの低下を持続させ、その結果脱灰時間が延長して う蝕の危険性は増加します。 また就寝中は唾液の分泌が減少しますので、就寝前の飲食はう蝕の危険性が高まります。 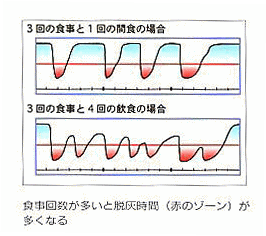 「実践カリオロジ−」より引用 ・食事指導の要点 指導の要点 飲食の回数を少なくすることを基本とします。(例:おやつとジュースは同時に食べる) 飲食回数を減らすことで、pHの低下時間の総計を減らすことができます。 おやつの食べ方・与え方 おやつに砂糖は切り離せないものです。砂糖は動物にとって重要なエネルギー源ですが、 摂取する量、摂取方法がむし歯予防には大変重要なポイントになります。 1日におやつとして食べる糖分・・・20グラムくらい おやつに記載された糖分量に注目しましょう。 「ダラダラ食い」はやめましょう 口の中に長い時間糖分を置かないようにします。乳児がほ乳瓶でジュースや イオン飲料を持続的に飲むのも要注意です。 おやつの種類を選びましょう 糖分が長い時間停滞するような種類のものは控えます。 特にアメ、チョコレート、ガム、清涼飲料水、乳酸菌飲料は要注意です。 甘いものと甘いものの組合せは避けましょう 甘いお菓子には水、お茶、牛乳を組合せて糖分をなるべく薄めましょう。 のどが渇いたときに欲しいのは水で砂糖水ではありません。 むやみにジュースを飲ませるのは避けます。 食べるならば、上手な食べ方と食後の歯磨きを忘れないようにしましょう。 ・非う蝕誘発甘味料(キシリトール)の利用 非う蝕誘発甘味料は、酸が産生されないだけでなく、再石灰化を促進させる唾液の分泌を促します。 唾液分泌が少ない人や甘いものがやめられない子供などにも有効です。 唾液分泌が少ない人に対しては、1日3回(毎回最低5分以上)シュガーレスガムを噛む 訓練を行うことによって、分泌量の増加をみることがあります。 キシリトールとは? キシリトールは白樺や樫などの樹木から採られたものが原料となる甘味炭水化物のひとつです。 予防薬品と思われがちですが、キシリトールは食品で、以下の作用が期待できます。 1.微生物学的作用 細菌によって発酵されないため、酸が産生されない。 細菌のエネルギー源として使用されないだけでなく、細菌の貯蔵エネルギーを消費さ せその生育を阻害する。 2.唾液分泌促進による再石灰化の促進 キシリトールの甘味による唾液分泌の刺激。重炭酸塩イオンの分泌と生成を刺激。 3.生物無機的作用 カルシウムイオンの沈殿を阻止することで、唾液中のカルシウムイオンの過飽和 状態を維持し再石灰化を促進。 キシリトールを摂取する方がミュータンス菌の感染率が減少する。 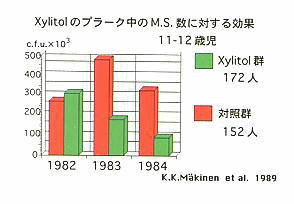 |
|
| (3)宿主 ・歯質 解剖学的形態 萌出直後の歯は小窩裂溝が深く、プラークが停滞しやすいために、う蝕が発生しやすい。 構造的要因 萌出直後の歯は石灰化レベルが低く、脱灰しやすく、う蝕が発生しやすい。 ・歯列 歯列不正(特に叢生)がある場合には、プラークが停滞しやすいために脱灰しやすく、う蝕が発生しやすい。 ・唾液 むし歯になりやすいかどうかは、唾液の量(分泌量)と質(緩衝能)にも関係します。 唾液の抗う蝕作用・・・緩衝作用、洗浄作用、カルシウムイオンの供給、など。 唾液の分泌量 1.部位による分泌量の違い 診察室においてフッ化物塗布を行うあたっては、口腔内の唾液の流れを考慮して おく必要があります。 唾液の流れのよい部位では塗布したフッ化物は急速に流されてしまいます。 しかし、このような部位では炭水化物や細菌によって産生された酸の浄化も効率 的に行われるためにカリエスリスクの低い部位であると考えられます。 逆に、唾液の流れの悪い部位は炭水化物や酸の浄化に時間がかかるために、 カリエスリスクも高くなります。 しかし、フッ化物も停滞しやすいために高いう蝕予防効果も得られやすいということ になります。 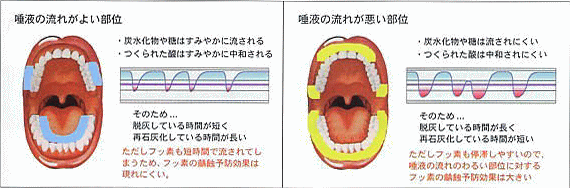 2.時間帯による分泌量の違い 日中に比べ、睡眠時には唾液の分泌が減少します。 したがって就寝前の飲食は控え、加えて就寝前のブラッシングはう蝕予防に効果的です。 3.加齢による分泌量の違い 加齢が唾液の分泌量に与える影響は比較的少ないと言われています。 70歳以上になると唾液腺の萎縮に伴う唾液分泌の減少もありますが、多くは 何らかの基礎疾患により処方されている薬剤の影響が高いとも言われています。 〈薬剤による唾液分泌抑制〉 利尿剤・・・マンニトール、クロロチアジド、トリアムテレン 降圧剤・・・ベタニジン、レセルピン、ニフェジピン 抗ヒスタミン薬・・・アレルギン、ネオレスタミン 抗うつ薬・・・トフラニール、ネオレスタミン 抗コリン薬・・・アトロピン、ボルタレン、イブプロフェン 鎮痛薬・・・モルヒネ 気管支拡張薬・・・エフェドリン 骨粗鬆症治療薬・・・エルシトニン、エルカルシフェノール 唾液の質(緩衝作用) 唾液には、口の中の環境を一定に保つ作用があります。 特に、酸性に傾いた環境を元に戻す作用を緩衝能といいます。 緩衝能が高ければ、脱灰時間(赤のゾーン)が短く再石灰化の時間 (青のゾーン)が長くなります。 逆に緩衝能が低ければ、脱灰時間が長いだけでなく再石灰化の時間がなくなってしまいます。 そのために緩衝の低い口腔では、う蝕が発症しやすくなります。 唾液分泌速度が速くなれば重炭酸イオンの分泌が高まるために緩衝能が高くなります。 安静時唾液は分泌速度が遅いので緩衝能は低いです。 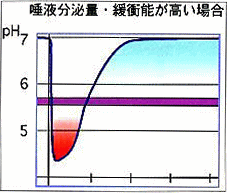 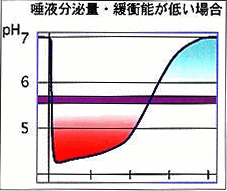 「実践カロオロジ−」より引用 「実践カロオロジ−」より引用・フッ素について 定期的に繰り返し塗布することで歯質を強くし、むし歯になりにくくします。 しかし、フッ素を塗布しただけで全くむし歯にならなくなるわけではありません。 日常のブラッシングが行われていなければ、フッ素の効果は十分に期待できません。 あくまでも補助的方法として考えてください。 フッ素とは? フッ素は通常NaF、CaF2などとして存在し、歯質の強化、う蝕原因菌の活性を阻害してう蝕の発生を 抑制します。 歯に対する作用 1.フルオロアアパタイトの生成 フッ素が萌出後の歯の表面に直接作用して、ハイドロキシアパタイトから フルオロアパタイトを生成してエナメル質に耐溶解性を与えます。 2.結晶性の向上 エナメル質結晶の格子不整を修復して、う蝕抵抗性を与えます。 3.再石灰化 フッ素は唾液中のカルシウムイオンやリン酸イオンとともに歯に再沈着して 脱石部分の再石灰化を促進します。 口腔内における作用 細菌・酵素作用の抑制・・・細菌が産生する酵素(エノラーゼ、フォスフォグリセロムターゼ) の活性を阻害して、むし歯の発生を抑制します。 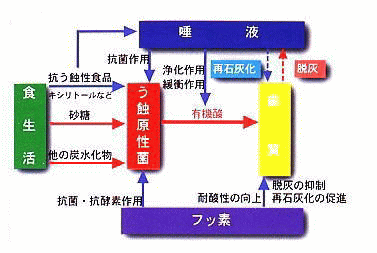 フッ素の応用 ホームケアにおけるフッ化物利用 歯の結晶構造の安定化は、イオンのやりとりが繰り返されることによって起こります。 このことから考えると、ホームケアにおいて大きなう蝕予防効果を得るためには、単に 高濃度のフッ化物を用いるよりも、たとえ低濃度であっても頻繁にフッ化物を使用する ことが重要であると理解出来ます。 診療室におけるフッ化物塗布 診療室においてフッ化物塗布を行うにあたっては、口腔内の唾液の流れを考慮しておく 必要があります。 |
|
| このページのトップへ戻る |
|